千葉県市原市が生活保護受給者や身元が分からない人の遺骨57体を庁舎内のロッカーに保管していたことが同市への取材で判明した。保管が3年以上に及んだ遺骨もあり、同市は厚生労働省に「不適切だった」と報告。識者は「死者を冒とくする行為だ」と指摘している。
毎日新聞 千葉・市原市 ロッカーに遺骨57体 生活保護受給者ら より一部抜粋
全く身寄りがない生活保護受給者の方が亡くなった際、骨上げした遺骨を供養せずにそのまま保管していたということでしょうか。
平成25年度のデータによると市原市の生活保護世帯数は3372世帯となっております。
経験による予測ですがこのぐらいの世帯数ですと大体年間に180~250人の方が亡くなる計算です。
さらにその中で身寄りのない割合となると年間で25人~50人くらいになるのではないでしょうか。
そのため、身寄りのない生活保護者全ケースがロッカーにしまわれていたわけではなさそうです。
ただの推測でしかありませんが、永代供養などの方法がまったくなかったわけではなく、適切な処理方法がわからない係があり、そのままロッカーに置き続けたことによって一部係のみ慣習化してしまったのではないでしょうか。
自治体ごとに葬儀等の流れに違いがあることも
違いがあるといっても最終的にしっかりと供養されるという点では同じです。
規模が大きな自治体ですと、生活保護の葬祭扶助額(180,300円上限)で遺体の引き取りから安置、火葬場までの移動、火葬後の骨上げ、永代供養も全てやってくれる葬儀会社があり、こういう場合はケースワーカーもあまり手間を取ることがなく負担が少ないです。
しかし葬儀会社自体が少ない自治体の場合は、一部の業務についてはケースワーカーが動かなければいけない場合があります。
流石に引き取りや安置といった事は葬儀会社がしてくれますが、火葬場までの移動後(骨上げ、お寺への永代供養依頼)は全てケースワーカーがすることもあります。
私の場合がまさにそれで、多いときには年間で8件ほど骨上げをしました。
一人だけでする骨上げは寂しいものがありますが、自分一人しかいない分しっかりと最後のお別れをすることができたかと思います。
最後の方になると喉仏については葬祭場の職員さんから言われなくても「あ、これですね」とすぐにわかるようになりました。
体調の悪化で入院し、そのまま…なんてことがわかってくると、それとなくケースワーカーから
「万が一の時に葬祭についてお願いできる人がいませんか?」
とは毎回確認するのですが、やはり人によっては全くいない、いたが既に他界してしまったという事が多いです。
葬祭については葬儀会社との連携が不可欠です。
葬儀会社もビジネスであるため、葬祭扶助額内に収めようとすると人件費等抑えなければいけない部分もあります。
そういった点も配慮しながら、良い葬祭扶助の流れを確立し、適切な葬祭執行を行いましょう。
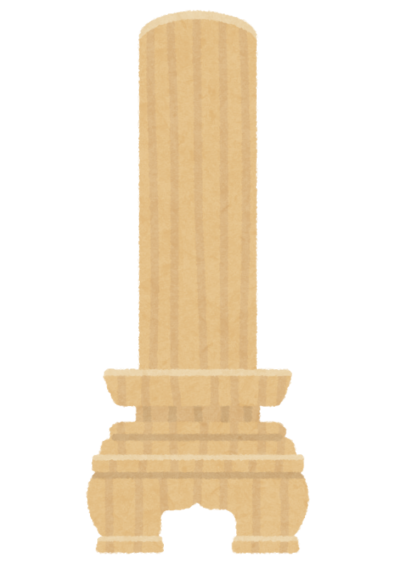


コメント
遺骨は、「引き取り手」がいつ現れるかわからないので、(あとから出て来て「返してもらえない」と言われたら揉める)
どこかの部署で保管するのだと思います。
役所が特定の宗教行為は出来ないから、
ただ「保管」だけでしょう。
もんと様 コメントありがとうございます・
通常は「返してもらえない」と揉めるのを防ぐために近隣のお寺に協力をしてもらい永代供養を行います。
そのため「役所で保管」するという対応についてはどんな事情があるにせよ基本的にはまかり通ることはない行動です。